当記事は以下のような方におすすめです。 本文はコチラから。
- 他の人よりちょっと得意な知識を身につけたい
- 歴史は学生時代ちょっと得意だったから見直して知識を強化したい
- 学生時代、歴史苦手なのがコンプレックスだったから克服したい
私は自信がない方に知識を身につけることをオススメしています。不安を減らし、自信を築く土台になると思っているからです。

どういうことなんだぜ?
たとえば自己紹介や自己アピールする時。自分の中で何か一つでも好き、得意で語れることがあれば堂々と話せるでしょう。
普段から「自分には話せることなんて何もない。話題振らないで」と怯えることもありません。
「誰よりもとは言わないけど、普通よりは知っている知識」
を持つことで、自分を少しでも認めてあげられるようになるはずです。
私自身の体験も含めて、知識と自信についての詳細は>>知識を身につけて自信をつけよう!で書いておりますので、良ければコチラもご覧ください。
今回はそんな知識の一つ【日本史】についてやっていこうと思います。

歴史か!
俺っち、ああいうロマン感じるの好きだぜ。
コンセプトは「 読んだ後、誰かに話したくなる知識 」です。
メインの「書籍の内容」+「私が調べた豆知識」も載せています。気になった方はご自身でも調べてみてくださいね。
ちなみに当記事はシリーズとなっております。他の記事は>> 知識を身につけて自信をつけよう! 【日本史】よりどうぞ。
【日本史】旧石器時代編
今回の記事を書くうえで参考にさせていただいたのがこちら。
「一度読んだら絶対に忘れない日本史(著者: 山崎圭一 )」
歴史を学ぶ上での参考書籍、著者の山崎さんは教師をされています。YouTubeもされていますので興味のある方はHistoria Mundiへどうぞ。日本史だけでなく世界史もされていますよ。
配信を始められたきっかけについてはオリラジ中田さんとのコラボ動画にて語られています。中々感動する面白いきっかけです。
書籍はカラーやマップ、図を上手に組み込まれており、非常に分かりやすく、面白い。
学生時代にお会いしたかった!
そしてなにより、年号が使われていないのが特徴です。
歴史の本というのは途中途中でぶつ切りになっていることが多いのですが、それを避けるような構成になっており、全体のストーリーを掴むこと、をテーマに作られた書籍となっております。
歴史好きな方はもちろん、苦手だと避けてきた方にもおすすめです。

それはいいから、早く歴史の勉強に入ろうぜ(わくわく)
前置きはこれくらいにして、やっていきましょう!
日本列島が出来たのは約一万年前――気候変動により誕生

↑のように日本列島が出来たのは約1万年も昔。
今は西暦で2021年ですが、その暦ができるよりもはるか昔の話になります。

中国とかと陸で繋がってたんだっけか。
そうです。それが気候変動により大陸と分断されました。
この気候変動前と変動後で時代に名前がついています。
気候変動前が更新世(こうしんせい)=旧石器時代。
気候変動後が、完新世(かんしんせい)=縄文時代。
今回は日本最古の「更新世(旧石器時代)」を学んでいきます。
更新世(旧石器時代)の3つのポイント
旧石器時代と呼ばれるこの時代を3つに分けて解説。
- 更新世と旧石器時代――なぜ名前が複数あるのか
- 日本の始まりは旧石器――アマチュア考古学者の熱意が歴史を変えたっ?
- 旧石器時代の生活――気候、文化、道具
一つずつ見ていきましょう。
更新世と旧石器時代――なぜ名前が複数あるのか

どっちも同じ時代のことなんだよな?
なんで2つあるんだ?
これは何を基準に時代を判断するか、という違いになります。
更新世(こうしんせい)や次回の記事で紹介する完新世(かんしんせい)は地質年代(理科)における分け方になります。
ちなみにこの時代にはもう一つ呼び名があります。
それが……『氷河時代(期)』
これは歴史嫌いの方でも聞いたことある単語だと思います。
何回も起きた氷期と呼ばれる気象による名づけと、文化の在り方として社会科の見方で旧石器時代という呼び名がついているわけです。
色んな分野から見るだけで名前が変わるのも面白いですね。
日本の始まりは旧石器――アマチュア考古学者の熱意が歴史を変えたっ?
昔、旧石器時代に日本には人間は住んでいなかった、という説が当たり前でした。

あれ、そうなのか。
でも……なんでだ?
と言うのもこの時代の日本の地層には厚い火山性の堆積物の層がありました。つまり火山活動が活発だったということです。

なるほどな!
だから人間は住めねーっていう判断か。
人骨でも見つかれば別だったでしょうが、日本では酸性の土壌が多いため土の中で消滅しやすく、人が住んでいた証が見つかりにくかったのも要因ですね。
人類の進化は猿人・原人・旧人・新人。
日本で見つかった最古の人類は新人で、沖縄県の港川人(みなとがわ・じん)や静岡県の浜北人(はまきた・じん)など数例しかないほどです。
そのため長い間、日本の始まりは縄文時代と思われていました。
そんな中で行商人でありながら独学で考古学を勉強していた群馬県の相澤忠洋(あいざわ ただひろ)いう人物が、偶然にも崖の関東ローム層から明らかに人が加工した形跡のある石を発見したのです。
太平洋戦争が終わった翌年のことでした。

独学、つまり素人か!
そうです。学者ではない、アマチュア考古学者、です。
それゆえに誰もが彼の言うことを信じませんでしたが、彼は群馬から東京まで何度も自転車で往復して説明して回り、ようやく本格的調査が始まりました。
その結果として多数の打製石器が出土し、更新世の地層から旧石器時代の痕跡が認められました。
この瞬間、日本の始まりの歴史は2万年以上もさかのぼることになったのです。

熱意がプロたちを動かし、歴史を動かしたのか!
くぅっ熱い話だぜ!
ええ、本当にそう思います。
ちなみにこの発見された遺跡――『岩宿遺跡(いわじゅく・いせき)』では古いもので3万5000年前の打製石器が見つかっています。

相澤忠洋
日本人の祖先の生活に思いを馳せ、孤独の中から到達した岩宿こそ、私という一人の人間に刻まれた二十三番目の年輪であった。
「岩宿」は、青春の日の輝かしい思い出であり、また私の人生の記念碑でもある。
(相澤忠洋著「岩宿の発見」より)
写真:相澤忠洋記念館(HP)
旧石器時代の生活――気候、道具、住居、食べ物
気候。氷河期と呼ばれる時代ですから当然寒い気候だったでしょう。

そういや寒さをどうやって乗り越えたんだろうな?
だって今みたいに暖房もまともな防寒具もないだろ?
そうですね、本には載っていませんでしたが気になったのでググってみました。
そうすると寒さに強いネアンデルタール人と交配して寒冷への耐性をつけていた、という記事を発見しました。
『現人類、ネアンデルタールと交配で寒さ耐性獲得 研究』(AFP BB News)。
本当かどうかまで私に判断はできませんでしたが、少なくとも現代人よりは寒さに強かったのでしょうね。
気になった方は「ホモサピエンス 寒さ」などで検索してみてください。新人、で検索すると経験の少ない新しい人、という意味になってしまうのでホモサピエンスとするのがポイントです。
しかし寒さだけでなく、日本では火山が活発に活動していました。先祖はさぞかし苦労したでしょうし、火山が噴火するたびに恐怖していたことと思います。
この時代、人間が生きていくにはかなり厳しい気候だったのです。
道具は旧石器。これは石を打ち欠いて作る打製石器というものです。
※写真は複製による復元品です。 ナイフ形は直接手に持って使用することもあったようです。
石を打って刃をつけた石斧やナイフのような石器があります。刃物はもうこんな時代から存在していました。

石斧や石のナイフ……刃ってどの程度の切れ味だったんだろうな?
切れ味悪そうなイメージがありますね。
ですがただの石ではなく、天然のガラスである黒曜石や割れると角が鋭くなる性質のサヌカイト(讃岐岩)が使われていました。
この黒曜石は手術用のメスとして使われるほどに切れ味が鋭いので、十分に実用性があるものです。
そして道具は進化していき、尖った石器を取り付けて槍先にした尖頭器、小型の細石器も用いられ始めます。
細石器などは刃こぼれしたらその部分を取り換えて使っていたようです。エコですし、利便性に優れていますね。
古代の人々は私たちが思っている以上に便利な道具を使っていたらしいですね。
石器についてさらに詳しく知りたい方は『日本旧石器学会』『宮崎県埋蔵文化財センター(旧石器時代・石材学習キット)』へ。

へー、なんか意外だな。
あれ? でも黒曜石なんてどこでも採れるもんじゃねーよな?
よくご存じですね、親方。
その通り! 黒曜石は採石できる地域が決まっています。特に日常で使うわけですからある程度上質なものを求めるとさらに限られます。
が、道具は日本各地に散らばって発見されている……つまり、かなりの広範囲で交換、分配が行われていたということです。

交易みたいなことしてたのか!
ということは、もう言語ははっきりしてるのか?
言語に関しても本には載っていません。がこれもググると面白いですよ。
『なぜ言語の発生時期を5万年前後と考えるのか?』(生命誌研究館)
こちらの記事はちょっと専門性が高くて完全に読み取れませんでしたが、5万年前には言語と呼べるようなコミュニケーションツールがあったのでは、というお話です。個人の見解ではありますが、興味深いですね。
本当に言語があったとしても、もちろん今のような言語とはまた違っていたでしょうけども。

身振り手振りでも交換はできなくないだろうが、見ず知らずの相手に切れ味の良い石を渡したくはねーよな、普通は。
会話は漫画や映画とかである「うほっうほ」とかいう感じかな?
どうなのでしょうね。
あと私が気になるのは言語があったとして、この時点で地域性……つまり方言みたいなものはあったのか、ですね。

なんかこう、細かい疑問考えたり調べていくと面白いな!
特に古代だからか?
分からないことが多い分、想像できますからね。
住居はテントのようなもので、移住生活を送っていたと考えられています。

「第2章 先史時代と川 第3章 アイヌ文化と川 第4章 十勝開拓と川」より
1集落の人数は少なく、他の集落との関りは少なくともあったと考えるのが上記の道具のことからも自然でしょう。
食べ物ですが、肉を生で食べていたイメージですが、熱した石で肉に火を通していた形跡があるそうです。

そんなことまで分かるのか!
結構グルメなのか?
グルメという考えも否定はできませんが、殺菌や食べやすくするためも大きいでしょう。
生肉からはビタミンが摂れるとはききますが、寄生虫や細菌がいる可能性が高いです。祖先たちの体が現代人より頑健だったとはいえ、衛生環境が良いとは言えませんしね。
また、顎も大分小さく進化してしまったため、生肉そのままはきつかった可能性もあるそうです。

それもググったのか?
はい、ググりました!
『人類はいつから食べ物に火を通すようになったのか。どうして肉を焼くのか』(ハトスク)
他にも検索結果たくさん出てくるので、気になった方はぜひ調べてみてください。
【まとめ】旧石器時代とは
- 理的・社会・気象的考えにより、複数の名がある(更新世、旧石器、氷河期)
- アマチュア考古学者の熱意により2万年以上日本の歴史がさかのぼる
- 寒い上に火山活動が活発、非定住生活を送る。獲物は大型哺乳類。言語があったかも?
間に私の気になったことも差し込んでしまいましたが、どうだったでしょうか?

俺っちはすっげー、楽しかったぜ!
うん、まあ親方が楽しんでいただけたなら良かったです。
ここまで読んでいただいた方の中にも、楽しんでいただけた方がいらしたらとても嬉しく思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございまた! ではまた次回、お会いしましょう!

おうっ!
また会おうぜ!
今回参考にさせていただいた書籍がこちら! とっても面白くてスイスイ読んじゃうのでお勧めです!
その他参考にさせていただいた資料・サイト一覧(敬称略)
AFP BB News
>>『現人類、ネアンデルタールと交配で寒さ耐性獲得 研究』
相澤忠洋記念館
>>『相澤忠洋について』
日本旧石器学会
>>『旧石器はどのように使われたの?』
宮崎県埋蔵文化財センター
>>『旧石器時代・石材学習キット』(石器の種類一覧)
生命誌研究館
>>『なぜ言語の発生時期を5万年前後と考えるのか?』
国土交通省北海道開発局
>>『第2章 先史時代と川 第3章 アイヌ文化と川 第4章 十勝開拓と川』
ハトスク
>>『人類はいつから食べ物に火を通すようになったのか。どうして肉を焼くのか』


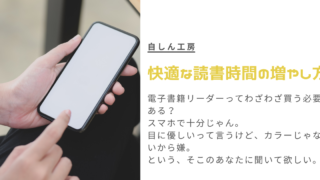
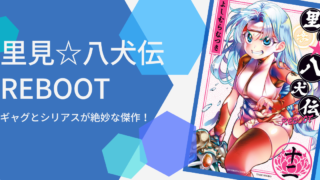




コメント